| 2025年3月31日(月) |
| 春を迎える準備作業 |
早いもので、今日は3月の最終日。
明日から4月、いよいよ実質的な春である。
昨日雪が降ったとはいえ、もはや積もることは無かろう。
先日行った、猪用電柵の修理もその一環ではあるが、春を迎えるための作業を行うべき時期になってきている。
昨日に続いて気温は低めであるが、天候は一転して晴れの良い天気。
春を迎えるための作業を実施することにした。
作業は昨年「冬支度」として行った雑木の雪囲い こちら→(2024/12/1)
の撤去である。いわば「春迎え」の作業である。
「冬支度」という造語はこれまで長年にわたり使ってきたが、「春迎え」という言葉はこの度初めて作った造語。
今後は時折使って見ようかと思っている。
さてその作業、行ったのは午後である。
写真左側が撤去前、右が撤去後である。
黒いテープで縛っていて、分かりづらいので、赤丸印をつけてみた。
元々この雪囲いの作業は、実施しているのが風景の邪魔にならないよう、工夫して実施している。
作業前後の区別がしにくいということは、逆に言えば施工方法が成功であった、といってよいのであろう。
要した時間は1時間弱。
ともかくこれで「春迎え」の作業が一つ終了した。
|
|
|
|
| 2025年3月30日(日) |
| おそらく 終雪 |
朝、一仕事終えて窓のカーテンを開けると雪が降っていた。かなり大粒の雪である。
スマホで天気予報を確認すると、午前11時頃まで雪が降るとなっていて、それを元に今日一日の行動予定を頭の中で描いたりする。
ところが、11時頃になっても、まだ雪がちらつく。
再度スマホを開けて予報を見たら、今度は午後の3時頃まで雪と予報が変わっていた。
ならばこの間にと、雪が薄くなった時を見計らってウォーキングに出てみたが、思いのほか雪の降りようが強く、身支度も悪かったので、ウォーキングを中止して家に戻ったほどである。
午後になり、一時止むこともあったが、結果としては夕方まで雪が降り続くことになる。。
こんな中、Mが雪の降る様を動画に収めた。
こちら→
梅の花が咲く中で雪が降ることは、たまにあるが、今年は梅の咲く時期が2週間ほど遅れた中での雪で、やはり珍しい現象といってよかろう。
冬が終わり次の春になって最後に降る雪のことを「終雪」と言うらしい。
八色石において、今回の雪が「終雪」になると期待したいものだが、3月30日を記録すること事態、これまでに無かった事と思われる。
|
|
|
|
| 2025年3月29日(土) ラベル329 |
| 私の履歴書 中学時代 「送辞」の文が残っていた |
私の履歴書シリーズその11である。 前回は こちら→(2025/3/25)
関係ある回は むしろ こちら→(2025/3/24)
今回は、蛇足の回である。
通知表などと一緒に、卒業生に贈る「送辞」の原稿が出てきた。
おそらく2年生のときに3年の卒業生を送る言葉として書いたと思われる。
生徒会長をやっていたため、その役を指名されたのであろう。
400字詰め原稿用紙で4枚。添削を入れてもらう為と思われるが、一行飛ばしで書いているので、実質は2枚。800字ほどの原稿のである。
その原稿に書かれた文章がなかなか良くできている。ただ今の自分が書くにしても、せいぜいこの程度の文章しか書けないであろう。それを中学2年生で書いているのであるから、少々驚きであった。
先生の添削の文字が赤インクで入っている個所が2ヶ所あるが、他はほとんど添削されていない。
大半、原文のままで完成となっていた。
ここにその文章を再現してみる。
注;赤文字は先生が添削された添削文字。それに続く()内文字が、元の原稿に記載されていた添削前の文字である。
送辞
寒さをしのぶ、梅花もすでに終わり、桜花もほころぶ春の訪れを身近に感じます今日、卒業生の皆様には、中学校の過程を終えられ、栄えある卒業証書を抱かれましたことを、在校生一同、心からお祝い申し上げます。
先ほど、校長先生の手より、一人一人卒業証書をいだかれた、皆様方(兄様姉様方)の希望と喜びに満ちあふれたお姿を見て、わたくしたち、自分のことのようにうれしく感じました。
皆様は、9ヶ年という学校の生活を今閉じて、新しい生活へ巣立たんとしておられます。強く羽ばたき飛び立てる、皆様をご覧になり、ご父兄のお喜びはもちろん、先生方もさだめしお喜びのことと拝察いたします。
思えば、ただただ懐かしいことばかり、汗を流して戦った球技大会。秋の運動会。楽しかった学習発表会。健脚を競った陸上競技大会など、限りない思い出が、走馬灯のように浮かんでは消え、消えては浮かんでまいります。皆様は、こうした数々の思い出をあとに去って行こうとしておられます。進学そして社会へと、そこには多くの厚い壁がゆく手をふさいでいることでしょう。しかし皆様が三年間この学校で、築かれたものを基礎(いしずえ)と(道具に)し、厚い壁をも打ち破り一歩、一歩前進してくださいませ。
私たちもそれぞれ一学年進級し、先生方のご指導をいただいて、皆さんの残された、立派な校風をより盛り立てて行こうと思っております。
“いかにして 誠の道にかなはなむ 千歳の中の一日なりとも”
良寛に教わったこの歌、口ずさみつつ強く生きてくださいませ。
今日これで、一応お別れは致しましても、どうか母校をお忘れなく、時々おたずねください。お待ちしております。
以上簡単ではございますが、在校生一同に代わりまして、皆様のご卒業をお祝いし、お世話になったお礼を申し上げますと共に、御健康御幸福をお祈りいたしまして、送辞と致します。
というものである。
末尾に2個所「ませ」という言葉が出るが、若干この個所が気になるだけで、あとは全く問題がない。
さらに良寛の歌を引用しているところは少々驚いた。如何なる経緯をへて、ここに登場したのか全く思い出せないが、しかし当時のK少年は、この場で引用する価値を見出していたのであろう。
この原稿を別の紙に書き写し、卒業式の日に読み上げたのであろうが、その卒業式の様子のこと一切が全く消え失せていて、何も思い出すことができない。
遥か昔のことになる。
|
|
|
|
| 2025年3月28日(金) |
| 「子供の日記」の文章 |
ただいま図書館で借りている本に関わる話である。
通常借りるときは、雑誌2冊(文藝春秋、暮らしの手帖など)と、単行本3冊を借りることが多い。
そのうち単行本に関しては司書が並べた特別の展示台があって、その中から借りることが多いが、その中で3冊に満たないときは、通常の書架をめぐって目ぼしいものを探してくる。
今回対象の本は、通常の書架でたまたま目に留まって借りたものである。
「天声人語」の歴代執筆者の中で、七代目にあたる方の著書。天声人語は1988年8月から1995年8月まで、7年間執筆に当たられたという。Kはこの方の名前をこれまで承知してなかった。
天下に名だたる「天声人語」の執筆者であるから、さすがに名文家である。
ただいま1/3程度読み進めたところであるが、その中に”我が意を得たり”という個所があった。
それが本日のタイトルに引用した「子供の日記」という言葉である。
氏は文章を書くにあたって、「子供の日記」に徹することにした、とされる。
この言葉を掲載する個所を上記の写真に添付した。
何に“我が意を得た”かというと、Kが小欄を書く時の状態がまさに、この「子供の日記」になっているからである。
ただ大きな違いもあって、氏の場合は初めから意図して「子供の日記」たる文章を書かれるのに対し、Kの場合は結果として致し方なく「子供の日記」になるという点が、大きな相違ではある。
話が少し反れるが、ここでKの場合の小欄の書き方について触れてみる。
氏は、ワープロに向かって文章を叩いたとされるが、Kはパソコンに向かって、音声で言葉を入力する。
まさにこの瞬間の写真を撮ってみると次になる。
パソコンのディスプレイ上には三つの画面が並べてある。左半分が散歩帖の編集画面。右上段がWordの画面、下段が散歩帖の本文を表示する画面である。
これまでに作成した文章などは、すでに左半分の編集画面に表示されている。
これから、次に入れる文章を入力するのであるが、その場合キーボードで入力するのではなくマイクに向かって言葉で喋る。するとしゃべった文字がWordの画面に即座に表示される。
表示されたWord画面の文字には、言い間違えや、聞き間違えなどの結果で誤った単語などが表示されることも多く、文章としては不完全である。
不完全な文章を整えて、文章を完成させるのだが、この部分は手作業によるキーボード操作である。
Word上で完成した文章を、コピーして、編集画面に貼り付けてゆく。
これも手作業である。
という風に、
編集画面では上から下に向かって順次、積み木を重ねるように文章を積み上げて行くので、出来上がる文章は「子供の日記」風にならざるを得ないのである。
これまで、自分で書いた散歩帖を読み返してみた時、構成に変化のない簡単な文章だなと、いつも若干ながら、引け目を感じていた。
これを、この文章の大家がそれでのだと言う。
“我が意を得たり”とは、そういう意味なのであった。
ついでなので、編集操作の説明をもう少し続けると、
編集画面で出来上がった文章一式を転送すると、「散歩帖本文」に反映される。
そして最終チェックとなるのだが、このときはWord画面を消して本文画面を右半分に拡大する。
右の本文を読み返し、微調整があれば左の編集画面で修正し、それを繰り返して完成となる。
小欄の記載にあたっては、当然のことながら、およその粗筋は想い描いて文章を書き始める。
しかし書き進むにつれて、横道に逸れたりし、当初の狙いとは外れることも珍しくはない。
今日もそんな形になってしまった。
これも「子供の日記」であるから致し方がない。
|
|
|
|
| 2025年3月27日(木) |
| 桜見物しながら電柵張り |
朝天気予報を見たら、八色石は11時時ごろから雨となっている。
もともとは、午後に予定していた昨日からの続きの電柵張りを、予定を早めて午前中に行うことにした。
9時頃からである。
昨日ほど温度は高くない。セーターを着て作業して丁度よい気温であった。
欅台の作業を終えて桜台にのぼり、桜台の作業もほぼ終えた頃気がついた。
桜が満開。見ごろである。
さくらといってもソメイヨシノではなく二期(四季)桜。冬を除いて、春から秋ごろまで年中花をつける。
そうは言いつつもやはりこの時期が見ごろ。花の数が倒的に多く色も濃い。
しばしの間作業をやめて、桜見物と洒落込んだ。
その後、義衛台の作業を終える。
作業はここまでで1時間半。
もともとの予定は、ここから下に降り町道沿いの電柵も修理するつもりでいたが、昨日からの腰が未だに痛い。
無理をすることはないと思い、しかも雲行きが怪しくなりつつある。
作業はここでやめて戻ることにした。
あと一日では終わらない仕事が残ることになったが、思わぬ桜見物ができたので、まあよし、と言うところである。
|
|
|
|
| 2025年3月26日(水) |
| 外仕事 第1号 |
今年は春の訪れが遅く、本格的外仕事は4月になってからと値踏みしていたのだが、昨日ごろから急に暖かくなり、陽気に誘われ本格的な外仕事を行うことにした。
行った作業は、対猪用の電柵の修理である。
ただし、昨日からジャガイモの種植えの手伝いをMに頼まれていて、その作業を1時間ほどかけて行ったので、電柵修理作業に着手したのは10時半過ぎからであった。
今日の対象区域は母家近辺の電柵。
予定では2時間程度を見込み、午前中のみでは終わらない。昼食を取って午後にも作業にあたった。
今日は特に暖かい。
午前中は着込んでいたセーターを脱ぎ作業に当たるほど。それでも若干の汗をかいた。
普段電柵の修理は、外見で見て異常な部分のみを修理するのだが、今回は少しばかり丁寧に行う。
支柱などでぐらつきはないか調べ、あるものには補強を施したりなどもした。
そんなこともあり、午後も2時間以上の作業をすることになった。午前中と合わせると3時間強の作業である。
作業を終えて母屋に帰り寒暖計を見ると24℃をさしていた。今年一番の暑さである。
電柵は母屋付近以外でもあちこちに設置してあり、その部分の修理も必要。。
最低でもあと2日は掛かる、と考えている。
本格的外仕事で、夕方からは少々腰が痛い。
|
|
|
|
| 2025年3月25日(火) ラベル325 |
| 私の履歴書 中学校時代 後日譚 |
私の履歴書シリーズその10である。 前回は こちら→(2025/3/24)
昨日の続きになるが、矢上中学校を卒業した同級生の後日譚である。
矢上小学校から別の中学校へ進級した人は別として、矢上中学校から高等学校へ進学した人の、進学先はすべて矢上高等学校であった。
矢上高等学校が発行した別の資料があって、出身中学別の入学者を示したものがある。
それによると、我が年次の矢上中学校から矢上高等学校へ進学した者の数は、普通科の男性が9名、女性が6名。農業科(全て男性)は12名、家庭科(全て女性)が9名となっている。
合わせると36名となる。
矢上中学校の卒業者数を57名とすると、高等学校への進学率は6割強という数字になる。
残りの人は就職したということである。
高等学校を卒業後、郷里の矢上に居を構えた人は数名いるが、中学を卒業して直ぐ就職した人の中に、矢上に残った人は誰もいなかった。全員が矢上を離れての就職と言う状況である。
昭和35年に中学を卒業したという時代は、戦後復興をほぼ遂げた時代とは言え、そういう状況であった。
以後、矢上高校に一緒に進学した人の若干の情報は別として、矢上小・中学校同窓生の情報はプッツリ途絶える期間が30年余り続くことになる。
私にとって旧交が復活したのは平成12年(2000年)である。
我々がこの地に戻ったのが平成13年であるから、戻る前年のこと、神岡部品に勤めていた時期にあたる。
「矢上小中学校卒業生名簿 ほたる」と題した冊子が郵送で送られてきた。
地元に残っている同窓生たちが作ってくれた冊子で、住所録のほかに、恩師や同窓生たちが近況を伝える文章と写真を寄せたもので、私も少年神楽団で三越に行った思い出を投稿している。
そしてその翌年の平成13年(2001年)夏に、我々はこの地に戻ることになった。57歳の時である。
以後いろいろな形で旧交を温めることになる。
節目の年には同窓会を企画した。
60歳の還暦、70歳の古稀、そして75歳を祝う会の3回。
前の2回では、恩師の先生方にもご参加いただいている。
中学の時の恩師藤井先生は、ご結婚され現在でも県内にお住まいで、同級生と一緒に2・3度お邪魔し馳走に預かった。
Mと一緒に伺ったこともある。
今なお往時の美貌を保っておられるのは、誠に喜ばしい。
話が少し転ずるが、藤井先生は先生を退職された後(と思われるが)、絣の織物を始められたらしい。
一方、若干ながらMも織物をする。そんな関係で藤井先生とMは懇意になった。
今ではKの知らぬ情報をMが所有することもしばしばである。
以前、藤井先生が学ばれた絣の学校の展示会が催され、その展示会の見学に行ったのもこのような経緯によるものであった。
こちら→(2020/12/11)
その後先生は、高齢になったということで、機織りをやめるという決意をされる。
機織機が不要になるので、Mに引き取ってもらえないかとの相談があり、Mが譲り受けることになった。
実家で軽トラを借りて先生宅に伺い、機織機を貰い受けてきた.。
したがって現在我が家には、Mが自分で買い求めた機織機と、先生から譲り受けた機織機が2台並ぶという格好になっている。
同級生の話をするつもりでいたが、話がだいぶ横道にそれた。
まあ、またこれもよし、と言うところである。
|
|
|
|
| 2025年3月24日(月) ラベル324 |
| 私の履歴書 中学校時代 |
私の履歴書シリーズその9である。 前回は こちら→(2025/3/17)
中学生時代のことに触れる。
昭和32年(1957年)4月、邑智郡石見町立矢上中学校に入学した。
入学を記念した写真が残っている。
同窓生の数を数えると58名のものが写っている。
以前小学校卒業時の写真を載せているが、 こちら→(2025/3/9)
このときは63名のものが写っていて、その時に比べると5名減っている。
学校の先生の息子で広島にある名門私立中学に進んだ同級生が一人、理由がわからぬが東京の学校に進んだ同窓生が一人、そして隣村にある邑智中学校に進学した同級生が複数いて、結果としてこのような数になっている。
クラスは小学校同様二つに分かれた。Kは1年1組。クラス担任の先生は藤井経子先生。若い美人の先生であった。
その後クラスは、2年2組で上村正先生。続いて3年2組で落合定信先生となる。
一方中学校は、小学校と異なり、具体的な授業は科目別となる。
思い出すままに列記すると国語は上田先生、生物は藤井先生、化学は服部先生、数学と物理は上村先生、地理は落合先生、英語は山本先生、そして音楽が谷口先生であった。
ただ具体的な授業の内容や授業風景のことなどすっかり忘れていて、何も思い出せない。
小学校時代と同様、中学3年間の通知表もすべて残っていた。
成績は3年間を通じて総じて良い。
敢えて分けると、良い科目が国語・数学・理科・体育、悪い科目が社会・音楽・図工・英語群となる。
人物所見も概して悪くないが、「も少し積極的に」とか「気が小さい」という言葉が出てくるところは、小学校時代と同じである。
中学になるとクラブ活動が始まる。所属したクラブは科学クラブと野球部。
野球部には2年と3年2年間所属した。ポジションはショート。夏休みに合宿した記憶がわずかに残る。
いつの時期だったか思い出せないが、郡大会に参加して、すぐに負けた記憶も蘇る。
一方科学クラブとしては、1年生のとき藤井先生に教わってシダ類の調査をした。原野に出かけ、シダ類を採集して帰り、新聞紙に挟んで標本作りをした記憶は強く残っている。
ところが、写真に残っている気象観測の方の記憶はほとんどない。通知表のコメント欄で2年生の記述の中に「今年度一年間、気象の研究によく努力してきた」とのコメントがあるので、何か具体的な事の調査をしてまとめたのであろうが、具体的に何をしたかの記憶がまったく残っていないのである。
もう一つ資料が残っていた。ホームルーム委員と生徒会長の任命書である。
ホームルーム委員とは、かつての級長で、1年生から3年生までの1学期に勤めている。先生の指名であったのか生徒間の投票で選ばれたのかは記憶がない。
一方はっきりしているのは生徒会長の方。こちらは生徒間の投票によって選ばれた。立会演説会があり、投票して欲しい旨の演説をした記憶がある。
任命書の日付は2年生の1月となっているから、2年生の3学期から任にあたり、1年間務めたものと思っていた。
ところが今回通知表を見ると、3年生の3学期も生徒会長を勤めたとの記述がある。なぜ1年以上なのかはよくわからない。
生徒会長として、「会則を改訂」したという記憶が残っている。
こうした経緯を経て中学校を卒業することになるのだが、卒業を記念する写真が残っていない。私がなくしたというより、おそらく撮られていなかったのであろう。
中学3年の秋、修学旅行で京都・奈良方面に出かけたが、その写真が多数残っていて、その中で一番格式ばったものを、卒業写真の代わりとして載せてみる。
同級生の数は57名になる。
入学時の写真より1名少ないが、1名数が減った理由を説明できない。
ともかく、昭和35年(1960年)3月に矢上中学校を卒業した。
田舎の中学校であるから際立った特色はない。
平凡だが、真面目に取り組んだ中学生活といってよいのであろう。
何事につけ、両親に指摘されたという記憶は全くない。全て自分の意志で決めたような気がする。
よく言えば自立心といえるが、逆に言えば我が儘を許してもらっていた、ものと思われる。
時代背景を探れば、卒業の前年には、平成天皇と美智子皇后が結婚され、また卒業の年には、第2次池田内閣が所得倍増政策を発表し、女性の平均年齢が70歳を超えたとある。
戦後復興をほぼ遂げ、世の中の動きが、いよいよ激しくなろうかというこの時期に、中学生活を終えたことになる。
|
|
|
|
| 2025年3月23日(日) |
| 遅れた春の兆し |
この3・4日、左足親指の付け根の関節が痛く、ウォーキングを休んでいたのだが、今日はひどく暖かい。
足に負担をかけないよう注意を払いながら、2日ぶりのウォーキングに出てみた。
その折に見つけた春の兆し。オオイヌノフグリである。
場所は「別棟」と呼ぶ場所の一角。
足が痛くなる前ウォーキングに出たときは、あちこちでこの花を探したが見ることができなかったので、おそらく昨日・今日の陽気に導かれて出てきたものと思われる。
それにしても、今年は春の訪れが遅い。
昨年この花の事に触れたのは2月13日。 こちら→(2024/2/13)
その文中で引用している2019年の月日は3月3日。
これらの記事から推察するに、今年は20日から一ヶ月近く、春の訪れが遅れているものと思われる。
その主因は、2月に襲われた複数にわたる寒波。
これも、異常気象の性によるものといわれる。
地球の将来のため、温暖化対策には本格的に取り組む必要がある。
とは言いつつも、風邪をひいては元も子もないと言い聞かせ、灯油ストーブを背ににしてこの記事を書いている、矛盾した身でもある。
|
|
|
|
| 2025年3月22日(土) |
| 今度は鳥すき焼き |
数日前、豚すきで好評を得たので こちら→(2025/3/16)
今度はトマト入りではないが、鳥すきを試してみることにした。
レシピは今回新たに探し当てたもの。
こちら→
材料はほぼレシピ通りのものがそろった。
椎茸は今春初めて採れた我が家の原木シイタケである。
焼きどうふは無かったので普通の豆腐にした。
レシピでは、はじめに鶏肉とねぎを油で焼くとある。
本来ならすき焼き鍋で焼くのであろうが、フライパンで焼く方が簡便であるように思われ、フライパンで焼いた後すき焼き鍋に移すことにした。
あとは予め作ったタレを入れて煮込むだけである。
さてその結果である。
Mの評価は、「おいしいが鶏肉がパサパサする」という。
その一両日前、同じ鶏肉で唐揚げを作ったのだが、そのときMは「肉がジューシーで美味しい」といっていた。
同じ肉なのに正反対の評価である。
前回の唐揚げのときは、鶏肉に下処理を行っている。今回すき焼きは無処理で焼いただけ。
次回また鳥すき焼きを作ることがあれば、鶏肉に別の下処理を施してみようかと思っている。
|
|
|
|
| 2025年3月21日(金) |
| 高校同級生のお孫さんが選抜出場 |
高校同級生のお孫さんが、現在進行中の選抜野球に出場した。
試合は今日の1回戦。所属するチームは広島商業、相手の学校は横浜清陵。
お孫さんの名は、名越選手。
強豪広商において、新2年生ながら、背番号7で4番を打つ選手であるから逸材である。
昨今高校野球はほとんど見ない我々であるが、今日だけは試合開始早々の9時からテレビで観戦した。
名越選手が出る場面を写真に撮ろうとスマホを出したら、あいにくスマホの電池が切れている。代わりにMが写真に収めてくれた。
試合は終始広商ペース。しかも途中から来客があって、テレビ観戦は中途で終了した。後刻試合結果を確認したら10対2で大勝をしていた。
話が少しずれるが、名越選手のおじいちゃんになる私の同級生も、ほぼ毎日ブログを発信している。
ブログ名は「権現砦」。 こちら→
ブログの中では、名越選手は若武者くんと呼ばれていて、もっぱら話題の中心になっている。
ブログを読むと同級生なるおじいちゃんは、昨夜から甲子園に応援に出かけているらしい。
帰宅後は、名越選手の活躍ぶりを、詳しく報告してくれることであろう。
|
|
|
|
| 2025年3月20日(木) |
| 気温測定データの整理 |
小欄ではたまに、当地の温度変化のグラフを掲載することがあるが、
例えば こちら→(2024/12/31)
その温度グラフの元になる測定データの整理をこの度実施した。
測定器本体は2016年に購入したもので、 こちら→(2016/8/12)
それ以降のデータをExcelファイルとして保存している。
保存したファイルのファイル名は、保存した日にちを基準にして名前をつけていて、年代順に並んではいるものの、データが重複していたり、あるいは電池切れほかの理由でデータが欠損している部分もあったりして、目的のデータを探し出すには若干の苦労があった。
ファイルの総数も40以上になっている。
行った作業は、これらのデータを整理して、1年分すべてのデータをExcelの1 Sheet上にまとめるという内容である。
具体的には、当該年度のファイルを順次開いて、1月1日分のデータからコピーし、予定した新たなシートに貼り付けていく。データが重複した部分はその部分を除いて、また貼り付けるという作業を繰り返すことになる。
データの最後は12月31日23時分の値になる。
測定データが1年分全部揃っていればこれで完了となるが、問題はデータがない場合である。
前述したように、多くの場合測定データが揃っていない。
このデータが揃っていない部分もわかるようにしてデータをまとめたいと考えた。
この場合欠損した日時、時刻を新たに作り出し、その値を当該シートに貼り付けて、測定データが欠落していることを表示しなければならない。
これが結構難題で、数年前に一度挑戦したことがあるのだが、そのときはうまくいかなかったという経緯がある。
と言うのは、Excelに書き出される測定ポイントの時刻を表す構造が複雑で、その再現がかなり困難であった。
もう少し具体的に言うと、測定した時刻の表示は次のように表示される。
「2023-11-22 15:45:15」
これは、2023年11月22日の15時45分15秒を表示していて、このルールに則って測定ポイントの時刻を作らなければならない。
前回は、この作業をExcelのオートフィル機能を使って作成したりなどしたのだが、結局時間がかかりすぎて断念したという記憶がある。
この経験を踏まえ、今回は別の作戦で臨むことにした。
測定ポイントを作成するExcel表を事前に準備するという作戦である。
ここで示した例は、2024年の8月分のデータを作成するものである。
年月の値はExcel表の左上で1度入力する。
測定時刻は、1時間に4回測定するという設定になっているので、その時間は、予め決めておき、00、15、30、45分の4回とする。秒は00秒である。
1ヶ月を31日とすると、1ヶ月のポイント数は、31×24×4=2976となるが、表では、このポイント時刻を瞬時に作成する。
表の背後には関数が記述してあって(緑の個所)、年月の値を入力した瞬間に、この2976個のポイント時刻が表示されるという仕組みである。
この作成されたポイントの中から必要部分をコピーして、用意したシートに貼り付ければ、希望の測定ポイントが完成するということになる。
この表を利用してデータ欠落部に相当する時刻を作成して貼り付け、1年分のすべての気温データを1シート上にまとめることができた。
一方これらのデーターをグラフ化するソフトは以前作成していて、こちら→(2016/8/31)
今回このプログラムを少し改良して、今回作成した年度別シートに合同し、一つのファイルに組み込んだ。
上の写真に示した例は、2016年から2020年までの温度データをまとめたファイルで、写真では2020年の一年間の温度データをグラフ化している。測定結果のなかった期間がグラフでは抜けている部分に相当する。
2021年以降の測定データは別ファイルとして保存した。
2016年から2024年までの年度別温度変化のグラフを示せば次になる。
2016年〜2020年
2021年〜2024年
今回の作業は、かなりの難事業で、一日にかけた時間はばらつきがあるものの、完了までに延べ6日の日数を要した。
それにしてもデータ欠落部が多いのには、自分ながら少々驚いた。
データが欠落する理由は、測定装置の電池が切れて測定ができないというケースもあるが、もう一つ大きな要因は、測定データが満杯になって、それ以降のデータ保存ができないというケースがある。
記憶容量は、1万6千ポイント分の容量で、1時間4回測定する場合ほぼ半年で容量が満杯になる。容量が満杯になる前にデータを保存して、データのクリアを行って次の測定に備えることをするのだが、その作業をついつい忘れて、満杯になって、記録ができない事態が生じるわけである。
今後は、注意をしなければと大いに反省した次第であった。
|
|
|
|
| 2025年3月19日(水) |
| お彼岸中の雪景色 |
2月中旬に降り積もった今年3度目の50cmほどの雪も、ここにきてほとんど消えていたのだが、一昨日の朝窓を開けて見ると、真っ白い景色で少々びっくりであった。
17日が彼岸の入り、あすが彼岸というこの時期になっての雪であるから少々驚きではある。
天気予報によれば日本の南岸を低気圧が通過中で、それに向かって寒気が降りているらしく、当地方でも大雪の可能性があるという。
結果的には昨日の夕方から一時強く降り、今朝の積雪で4・5cmは積もっていた。
ただし、このビックリ天気も今日までで、明日からは晴れの良い天気になるらしい。
夕方には、雲はなくなり晴れの兆しが見えてきた。
そういえば、昨年もこの時期に雪が降っている。 こちら→(2024/3/21)
びっくりするほどの出来事ではないのかもしれない。
|
|
|
|
| 2025年3月18日(火) |
| 老人会 会計業務の引継ぎ |
過日記載したように、 こちら→(2025/3/12)
集落の老人会である龍和会の総会において、会計係からの退役が承認された。
これを受け、今日今後から、今後会計を担当してもらう役員と、そしてもう1名の役員の2名の方にお願いし、会計業務の引き継ぎを行った。
引き継いだ資料は、私が前任の会計担当から引き継いだ書類のほかに、預金通帳や印鑑、さらにその他の総会資料などである。
そしてもう一つ引き継いだ資料がある。
それは会計用のパソコンソフト。
私が引き継いだ時は、会計業務は紙の台帳方式で行われていて、決算書まで作るとなると結構大変であった。それらの作業を、パソコン業務に置き換えたものである。
関係項目を一度だけ入力すれば、そのデータは通帳の払戻請求書や決算書などもろもろの帳票に即座に反映できるようになっている。
自分では、かなりうまく出来ていると自賛しているのだが、そのプログラムの使いかたも合わせて説明してきた。
今回引き継ぐにあたって、昔のパソコンファイルも覗いてみた。
作成済みの会計ファイルは平成25年のものからある。昨年の令和6年度まで合わせると12年分のファイルができていた。
記憶では、10年前後会計係を勤めた気になっていたが、実際は思わぬ長期間担当していたことになる。
来年からはいよいよ無役である。
無事に勤め上げたという安堵する部分がないでもないが、一方、年を重ねるとは任せてもらう仕事がなくなるということで、一抹の寂しさは残る。
仕方がないことと、自分に言い聞かせる次第であった。
|
|
|
|
| 2025年3月17日(月) ラベル317 |
| 私の履歴書 少年神楽団 大阪・東京公演 |
私の履歴書シリーズその8である。 前回はこちら→(2025/3/9)
話は中学生になってからの出来事であるが、中学生時代の具体的な話の前に、少年神楽団が結成され、大阪と東京で公演したという話にまず触れる。
というのは、この少年神楽団結成に、小学6年の時教えていただいた東先生が大いに関わっていたからである。
話の発端は小学6年の時の学芸会である。時期ははっきり記憶がないがおそらく晩秋であろう。
経緯は承知せぬが、その学芸会で、小学6年の担任の東・徳原両先生が、当時矢上で盛んに行われていた石見神楽を実演された。
写真が残っている。
具体的な経緯は承知せぬが、この神楽をきっかけに先生と神楽団団長の中村文太氏などの間で、少年神楽団と言う話が持ち上がったものと思われる。我々小学6年生の間で10名程度のものが選出されて練習に入った。
練習した演目は「鍾馗」と「大江山」。
述べる口上は、子供向けに先生らが言い回しを変えたものがプリントで配られた記憶がある。
私の役は鍾馗の臣(鬼を退治する側)。
多少間違っているかもしれないが、舞台に出て初めてのベル口上が、今でも思い出せば口に出る。
「そもそもこれは、神武天皇の功臣、四世の孫、摂津の守、源の安孫、頼経であるぞ」
その後中学になっても練習が続けられたものと思う。ただし具体的な記憶はほとんどない。
記憶があるのは、話が一気に飛んで、少年神楽団の大阪公演である。
時期は中学一年の9月(昭和32年)。
島根県の観光物産展が大阪のデパート高島屋で開催され、そのアトラクションとして少年神楽団が招待された。
公演は2日行われた記憶があるので、大阪滞在は3、4日であったのであろう。
写真には通天閣を見学したものが残っているが、写真に写っている以外の記憶はほとんど残っていない。
大阪公演の評判が良かったのか、翌年(昭和33年)の中学2年の時も、今度は東京の三越で行われた県の物産展のアトラクションで招待された。
このときは、隣村になる日貫の少年神楽団も一緒であった。
公演は三越の屋上で行われたのだが、公演の状況を示す写真は1枚もない。
修学旅行のような、東京都内を見物した写真ばかりが残っている。
国会議事堂前の記念写真には、当時の町長や矢上出身の県会議員も写っていて、ちょっとしたイベントであったのかもしれない。
行き帰りに乗ったのは蒸気機関車が引っ張る列車であった。トンネルに入ると、煙が窓から侵入してくる。大騒ぎしながら窓を閉めた記憶が残っている。
もう一つ列車から見た記憶。
昭和33年は東京タワーが完成した年にあたる。列車から見た景色の中に、東京タワーの展望台あたりまでが出来上がった、未完成の姿が見えた記憶に残っている。
この未完成の東京タワーの写真が残っているような気がして、今回あちこち探してみたが、結局見つけることができなかった。記憶違いであったのかもしれない。
東京公演の帰り途、列車が大阪駅に止まったおり、東(渡辺)先生が奥様共々ホームまで見送りに来てくれた。お2人とも和服姿。奥様の肩に真っ白いショールがかかっていたのが鮮やかに蘇る。
生まれて初めて見る大都会の実態に触れた。少年のころの貴重な体験になった。
余談;
ここに残る写真を誰が撮ったのかという疑問が残る。当時はまだカメラは高価で、誰もが持てる時代ではない。にもかかわらずスナップ風の写真がかなりの数残っている。
謎のままである。
|
|
|
|
| 2025年3月16日(日) ラベル316 |
| 豚肉でトマトすき焼き |
牛肉でのトマトすき焼きは、これまでに何度も作ってきたが こちら→(2023/6/9)
豚肉でのトマトすき焼きは初めてである。
我が家で牛肉を買うことは滅多にないが、豚肉の細切れは冷凍して常備してある。
Mに、「豚肉でやってみようか?」と話しかけると、「豚肉で?!」と返事が返るが、ものは試しで実行してみることにした。
豚肉は解凍してブライン液(水100cc、塩5g、砂糖5g)に4時間浸漬した。
後の手順はレシピ通りである。
(レシピは前掲引用の中で、2020年のページに載せている)
さて、そのお味であるが
まあ、悪くはない。
Mの評価も、「思ったよりは美味しいね」と言うところ。
今後夕食メニューに困った時の、“窮余の一策”にはなるかも、と思われた。
|
|
|
|
| 2025年3月15日(土) |
| 坂の上の雲 |
司馬遼太郎の手による「坂の上の雲」がNHKでドラマ化され、それがこのほど再放送された。
最初の放送は、1回当たり90分という長尺で、13回にわたって放送されている。
今回の再放送にあたっては、1回分を半分に分け、前編・後編とし、2回に分けて放送されたので、再放送の回数は26回になる。
放送されたのは日曜日の夜10時から。全ての回を録画し、録画したものをすべてみ終えた。
再放送の第1回が、昨年の9月8日で、最終が今年の3月9日である。
全放送を感動を持ってみ終えた。
目頭が熱くなるようなシーンもしばしばであった。
原作になった元の小説も手元に残っている。
昭和44年から47年にかけて上梓されたものだが、Kが読んだのは、印刷日から見て昭和48年頃と思われる。手に汗を握って読んだ記憶が残っていて、その後も1・2度は読み返した記憶もある。
我々が結婚したのが昭和47年の11月末。
新婚ほやほやの時期で、かつ仕事もかなり多忙を極めていた時期に、読み込んだらしい。
小説の内容は、出版社文藝春秋の宣伝文をそのまま引用すれば
「日露戦争において、世界最強といわれたロシアのコサック騎兵を満州の野に撃破した日本騎兵の創設者・秋山好古。その弟で日本海海戦の丁字戦法を編み出し、バルチック艦隊を屠った海軍参謀・秋山真之。その友人であり、近代短歌・俳句の祖正岡子規。伊予松山出身のこの三青年の友情と成長と情熱を、若々しく勃興してくる明治国家を背景に描き、健康な明治の青春を高らかに謳い上げた大長編小説。」
となっている。
感動を持って読んだだけに、この小説が大河ドラマとなって再現しないかと、当時考えたこともあったが、野戦あり、海戦ありの大スペクタルドラマ。とてもドラマ化は無理であろうと思っていた。
それがNHKによってドラマ化されたのである。
ただし放送を3回に分けた、3年がかりの制作になった。
第1回から第5回までが2009年。第6回から第10回までが2010年。第11回から第13回までが2011年。いずれも年末に放送されている。
我が家は、このときも全巻録画してDVDで保存した。
話が少しずれるが、昨年の7月頃、DVDで録画された映像を外付けHDDで見ることができるよう変換作業を行ったので こちら→(2024/7/1)
最初に放送された映像も、今では簡単に見ることができるようになっている。
2セットの録画を持っているという状況になってしまった。
逆に言えば、それほど入れ込んで見たドラマと言うことにもなる。
見逃した方にもお勧めしたいと、NHKオンデマンドを確認してみた。ただ今は配信をしている。
第1回は無料。その他の回は、1回あたり220円の有料である。ただ視聴期限が3月28日となっているものもあり、もし見てみようと思われる方は急がれるのがよい。
脚本よし、俳優よし、カメラワークよし、そして音楽もよし。
第一級のドラマと思われる。
NHKオンデマンドはNHKプラスとは異なり、コピーガードが掛かっていない(はず)。
普通の録画操作で録画できるはずである。有料でも、録画をしてみれば問題はない。
|
|
|
|
| 2025年3月14日(金) ラベル314 |
| 歌集「ゆふすげ」の紹介記事 |
以前、美智子皇太后様の歌集について触れたことがあるが こちら→(2025/2/6)
今回も同様の趣旨である。
今回はNHKでなく読売からの引用。
読売2面に毎日掲載される、長谷川櫂氏による詩歌の紹介コラム「四季」である。
3月1日から11日まで、10回にわたって掲載された(10日が新聞休刊日)。
美智子皇太后の歌集「ゆふすげ」から、10首を抜き出し紹介してある。
小欄読者にも読んでいただければと、二つの大きめな画像に分けて掲載した。
もとより、小欄筆者に詠まれた歌の批評などできるはずもない。長谷川櫂氏の添書きを待ってお読みいただければと思う。
歌集の歌もさることながら、もう一つ驚くべきことがある。
それはコラム「四季」の掲載回数。
ただいま7390余回の表示がある。
このコラム「四季」は、日曜日も掲載され、年中休みなしである。休みとなるのは新聞休刊日のみ。
掲載年数を計算すると丁度20年になった。
恐るべき継続力である。
|
|
|
|
| 2025年3月13日(木) |
| 2日掛で山水を出す |
今冬八色石は3度の寒波に襲われた。
1度目が1月初旬、2度目が2月初旬、そして、3度目が2月中下旬である。
積雪の量で言えば、1度目が30cm程度、2度目と3度目が50cm程度であった。
そんな中にあって、我が家の山水は2度目の寒波までは雪の中でも水が出続けてくれた。
山水が出ると出ないとでは生活の質が違う。
冬の間でも水が出続けるよう、秋口の間に、ホースバンドの増し締めをするなどの点検をする。
2度目まで水が出続けてくれたのは、これら長年の経験がものを云ったのかもしれない。
しかし、山水が出なくなる原因は数多くあって、出なくなるケースもしばしば発生する。
特に冬季の場合は特別で、一旦水が出なくなると手の施しようがなくなる。
というのはゴムホースの中が凍結して、春になって配管内が溶けるまでは手の施しようがないのである。
3度目の寒波で水が出なくなったのはそういう状態で、もはや対策の方法がなく、その後約一ヶ月間は山水が出ない状態が継続した。
そして昨日のこと、周辺の雪もほとんど消え、しかも気温がかなり上がっている。
龍和会総会から帰宅したあと、山水出しの作業を行うことにした。
今年になっての本格的外仕事、第1号と言っても良いかもしれない。
取水口近くのホースの接続部が一個所はずれていた。原因はよくわからない。取水口を見ると少々砂に埋もれてはいるが、水は出ている。
取水口の簡単な掃除を行って、外れた接続部をつなぎ直して、家に戻ることにした。
途中途中の接続部が外れていないことを確認して戻ったので、水は出ているはずである。
ところが、結果は予想に反して水が出なかった。
こうなると水が出ない原因探しの作業となる。
上から順に、途中途中の接続部を外して、ここまでは水が来る、という確認を順次行うという作業である。
結果としては納屋の横までは水が出た。
あとわずかの距離になって水が出ないのである。
放出口の近くになってホースは下屋の雪ずりの下を通る。この雪ずりの下の部分のホースが凍っているものと思われた。
雪ずりを掻いて、ホースを剥き出しにし、管内の凍りが溶けるのを待つことにした。
ここまでが昨日である。
そして今日である。
すべてのホースを繋いでみると、無事に放出口から水が出始めた。
作業としては2日がかり。
そしてほぼ1ヶ月ぶりの山水の出となった。
先人に教えられたことではあるが、こういうとりとめのない作業をこなして行くこと自体が生きることなんだ、と、自分に言い聞かせるようにしている。
|
|
|
|
| 2025年3月12日(水) ラベル312 |
| 令和6年度 龍和会総会 |
龍和会と言うのは、八色石集落老人会の名称である。
その龍和会の、令和6年度年次総会が開かれた。
当日は、総会、軽スポーツそして食事会という流れであったが、総会の雰囲気を伝える写真を取り忘れてしまった。
次の写真はその結果が反映されたものである。
Kは会計係なので、決算書や来年度の予算案などの報告をした。
役員である我々は9時から集まり、総会は10時から始まって、散会したのは2時頃であった。
今日の総会とは少し話がずれるが、Kがこの龍和会に入会したのは平成24年のことであった。
68歳の時である。
以後副会長と会計係を10年余り担当してきたが、80歳を迎えるのを期に、今年度(R6)から副会長職を、一昨年入会した人に担当替えしてもらい、会計係も来年度(R7)からその副会長に引き渡すことになっている。
来年度からはいよいよ無役である。
のんびりと参加させてもらうことになる。
以前、この会計係に関する小噺を小欄に載せていた。
余談ではあるが、参考までに紹介する。
こちら→(2017/3/16)
|
|
|
|
| 2025年3月11日(火) |
| 同級生逝く |
小学校から高等学校まで同じ学年を進んだ同級生がなくなった。女性の同級生である。
今日が通夜、明日が葬儀の日程であるが、明日は欠席できない用事があり、今日の通夜に参加してきた。
遺影は許可をいただいて撮ってきたものである。
この女性を語るには、もう一つ別の言い方ある。
亡くなった方は、小学校から高等学校まで同じ学年を進んだ男性の同級生の奥さんでもある。
つまり、今回なくなった同級生は、同級生の男性と結婚された、同級生同士の夫婦であった。
資料が重複するが一昨日掲載した小学校の卒業写真を再度載せてみると、当然のことではあるが、お2人が同時に写っている。
同級生の男性の方は、高校を卒業後地元に残り、農業一筋で頑張ったタフガイである。
亡くなった同級生はそのタフガイを陰で支えた。
しかも、結婚の時期は早かった気がする。高校を卒業してまもなく結婚されたような記憶がある。
笑い声の爽やかな女性であった。
ご冥福をお祈りする。
|
|
|
|
| 2025年3月10日(月) |
| ある日の夕食 |
2,3日前のことであるが、夕食を一人で食べるという事態が発生した。
前日の残り物ですますという手もあるが、たまたま大豆を水に浸して一晩置いたものがあったので、怠け心を押し殺して大豆料理を作ることにした。
水に浸した大豆を一度圧力なべで煮て、大豆の水煮を作った後、その水煮の大豆をさらに別の鍋で煮ると言う少々手の込んだ料理である。
参考にしたレシピは
圧力鍋で水煮を作る工程が こちら→
水煮した大豆を別の鍋で煮る工程が こちら→
である。
ただ、煮豆を作る工程のレシピは、謳い文句が「煮るのは10分」となっているが、ここは参考にせず、自分流の煮物を作る方法を採用した。したがって、1時間以上はかかっている。
自分流の煮物を作る方法とは、具材をあらまし味付けしただし汁で煮立てたのち火を消して一度さます。冷ます過程で具材に味が染み込む。冷ました具材と汁を再度煮込んで、最終の味に仕上げるという方法である。
出来上がった煮豆の味はなかなか美味であった。
写真の下段には、別の料理の皿が二つ並んでいる。
たまたまその前日の夕食当番がKで、その時の残り物。
一つが煮込みハンバーグでKの18番の一つ。参考レシピは こちら→
もう一つが、厚揚げと白菜の煮物。参考レシピは こちら→
白菜のあるこの時期にはよく作る料理の一つである。
三品並べてなかなか豪勢な夕食になった。
|
|
|
|
| 2025年3月9日(日) ラベル309 |
| 私の履歴書 小学6年生 続編 |
私の履歴書シリーズその7である。 前回は こちら→(2025/3/7)
前回触れた小学6年生時のことの、続きである。
今回は、先生に教わった“見えない形”のものに触れる。
“見えない形”のものとは何か、それは“読書”と“暗示”である。
最初に”読書”について触れてみよう。
小学5年生までは、本を読むという行為をほとんどした記憶がない。
そのような自分に、「本を読むという世界」があることを教えてくれた。
先生が勧めてくれた書名で記憶が残るのは、例えば
下村湖人著 次郎物語
山本有三著 路傍の石
伊藤左千夫著 野菊の墓
井上靖著 あすなろ物語
など。
全部の本を読んだとは思わないが、次郎物語だけは読んだ記憶が残っている。文庫本で3冊であったか。
おそらく先生が貸してくれたのであろう。
中に出てくる、「白鳥入蘆花」とか「無計画の計画」というフレーズは、今でも何かの機会に心に蘇ってくる。
これらのフレーズは、以前小欄で触れたことがある。
白鳥入蘆花 こちら→(2016/6/12)
無計画の計画 こちら→(2019/3/31)
ともかくこれを機に、私は本を読むようになったと、ありがたく感謝している。
次に“暗示”である。
暗示と言ってよいか、判らないが、
先生は私に、「K(私の名前の部分、よびすて)、お前は必ず大学に行け」と繰り返し呼びかけてくれた。
当時は小学生、その先に中学があり高校もある。
大学という名前は承知していたが、具体的な意味を持たなかった私にとって、その言葉をかけられる度に、“大学に行く”と思い始め、最後は“大学へ行かなければならない”と思う様になった記憶がある。
当時我が家の経済事情は、大学にまで進む余力はなく、通常なら、生まれ故郷で役場職員か農協職員になったであろう身が、無理をしながらも大学を目指すという結果になったのは、先生のこの暗示があったが故のことと、今更ながらに思うのである。
暗示とは少し話がそれるが、あまり記憶にない授業中の中で、一つだけ強く記憶に残っていることがある。
それは南極観測船「宗谷」の話。
宗谷は、我々が6年の2学期の時、東京の晴海埠頭を出発し、3学期になって南極に到着。南極のオングル島に上陸して「昭和基地」を建設し、第一次越冬隊を残して帰還した。
この帰還に当たって氷に一時閉ざされ、ソ連船「オビ号」に助けられる、などの逸話もある。
先生はこの話を授業の中で、「宗谷」の進捗に合わせつつ、熱く語った。
われわれはドキドキしながらその話を聞いたものである。
新しいものを見つけるという意味の重みを、この時味わったのかもしれない。
Kが、文科系より理科系の事柄により強く惹かれるようになったのは、ひょっとするとこういう体験がベースになっているかもと、思っている。
ともかくこのような経験を経て、われわれは矢上小学校を卒業した。
卒業写真が残っている。
同窓生の数は、63名となっている。
6年の時教えていただいた東先生は、我々を教えた1年のみで矢上小学校を去り、大阪の小学校へ転任した。
1年のみで転任された理由は、よくわからないが、その年に結婚され、姓が東から渡辺に変わっているので、結婚が決まっての転任であったのかもしれない。先生の結婚を告げる葉書が今私の手元に残っている。
先生はその後大阪の小学校で校長先生を務め、50余歳(のはず)で亡くなっている。
今回の記事を書くにあたり、先生の正確な没年を調べたが、正確な没年を得るに至らなかった。
先生は、矢上を去るにあたり、先生が使っていた机を私に残してくれた。
先生が大学に入学した時の記念の机である。その机は今でも我が家に残っている。
このことは以前記載したので こちら→(2016/11/1)
詳細は割愛する。
|
|
|
|
| 2025年3月8日(土) |
| マンサク 咲く |
今日の天候であるが、朝はうす曇、午後は晴れた。
午前中にウォーキングは済ましたものの、午後なんとなく春の雰囲気が感じられ、裏山散策に出てみることにした。
久しぶりの裏山散策である。気温は思ったより寒い。
少しばかり上がったところで、思わぬ黄色が目に入った。
マンサクが咲いていたのである。
辺りには、2月下旬に降った雪が、まだ少し残っている中での花のほころびであった。
昨年は、暖冬気味で早く咲いた気配もあるが、2月17日には咲いていて こちら→(2024/2/17)
今年は2月の寒波の影響を受けたものと思われる。
いずれにしてもマンサクは春を告げる花。
今年も無事に春を迎えることができる、と喜んだのであった。
殊の外、春を迎える喜びに浸ったという良寛の歌がある。
この里に手毬つきつつ子供らと 遊ぶ春日は暮れずともよし
霞立つ永き春日に鶯の 鳴く声聞けば心は和(な)ぎぬ
(中野幸次著「良寛に生きて死す」の冒頭で紹介されている)
|
|
|
|
| 2025年3月7日(金) ラベル307 |
| 私の履歴書 小学6年生 |
私の履歴書シリーズその6である。 前回は こちら→(2025/2/25)
小学校6年生時のことに触れる。
当時、5年と6年は同じ先生が担任することになっていて、5年生の末時当時の諏訪先生が、「来年も私が担任する」という趣旨の言葉を発せられた。
同窓生一同、「やった!」と叫んだ気がするが、それは忖度であって、本心はあまり喜びではなかったという気がする。
ところが、蓋を開けてみると、経緯はわからないのだが、違う先生が担任されることになった。
その先生は名を、東仁三という。
その年の3月に島根大学を卒業したばかりの、いわばピカピカの先生であった。
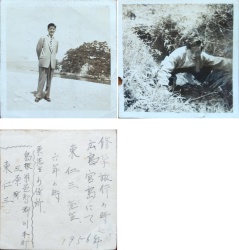
(下段は同上写真の裏書。
当時の自分の文字と思われ、記念に残してみた) |
学年は6年2組。
校舎は昭和31年に建設された新校舎になっている。 こちら→(2025/2/21)
最初の担任であり、先生にも期するものがあったのであろう、勉強やそれ以外のことなど、熱意を込めて教えていただいた。
先生は、当時最新と思われる二眼レフのカメラを持っていて、そのカメラで、いろいろな場面を写真に残していてくれる。
「ヤンボー」と名付けたヤギを飼い、夜、先生の下宿先へでかけて、勉強を教わったことが、何度もある。
また「原山」という、矢上から見てシンボルになる山に登ったこともあるし、「新山」という集落にでかけて走りまわった記憶もある。
先生は大学で、軟式ではあるが野球をやった経験があって、そのキャッチボールの相手をいつもさせられた。先生がピッチャーで、私がキャッチャー。捕手用のミットでなく普通のグローブで受けるので、手がひどく痛かった記憶が残っている。
また、下宿先を訪ねたときなど、よくタバコを買いに行かされた。
先生が吸うタバコは、缶入りの“Peace”で、缶を開けたとき、甘く、何とも言えない良い香りがしたの強く覚えている。
以上のような、“見える形”の事柄のほかに、”見えない形”のものについても数多く教わった。
次は、それらのことについて記述して行こうと思うが、今日はここで紙面が尽きた。
続きは、次回に回す。
|
|
|
|
| 2025年3月6日(木) ラベル506 |
| 定期健診 |
3ヶ月に一度の定期健診に行ってきた。場所は邑智病院。
前回は こちら→(2024/12/12)
新病棟に移って2度目の検診なので、手順に若干迷うが、あたりにいるスタッフを捕まえて聞けばさほど問題はない。
おいおい、慣れて行くであろう。
毎度申し上げるように、主目的はコレステロールと血液をサラサラにする薬をもらうことにあるが、
Kの場合、副次的に行われる血液検査の方が関心度は高い。
今回の医者の評価は、「規格値を外れている検査データもあるが、いずれの場合も許容値の範囲内である。すべての項目においてまったく問題はない。この状態を続けてください」という評価であった。
前々回の検査時に指摘のあったHbA1Cの値についても、今回は特別何も触れられなかった。
前々回の指摘に基づいて、昼食用の缶ビール(第3)の種類を、糖分を含な含まないものに変えているが、わが方もこれで一向に問題はないので、とりあえずはこの状態を続けていくことにする。
ともかく結果は、大団円となった。
|
|
|
|
| 2025年3月5日(水) |
| サロン田屋と公民館「ひなまつり」 |
今日は月2回開催されるサロン田屋の日。
参加を予定して昼食が作られるので、できるだけ参加するようにしている。
本日の参加者はスタッフも含めて9名。
昨今、参加者が少ない中では多い方であった。
今日の昼食のメインディッシュは天ぷら。
中に蕗の薹のてんぷらが入っていて、ほろ苦くて誠に美味。雪の下でも芽が出ていたのだという。
午後は、恒例の体操を早目に終えて、サロンが開かれる「田屋」からすぐ近くにある公民館で開催中の、「ひなまつり」を見に行くことになった。
「ひなまつり」は3日から開かれているのだが、見に行くのは今日が初めて。
今年も、賑やかに、見事に展示されていた。
展示の中には、Kが代表して作成した、 こちら→(2025/2/27)
老人会で作成中の方言集も展示されている。
主催者スタッフの説明によれば、結構熱心に読み入っている人もいるらしい。
方言集が完成した暁には、冊子にして、公民館にも届けると言っておいた。
一方Mの作品も展示されている。
今年のテーマは「色を楽しむ」として、自分で草木染めした糸を機織りした布などの作品ほか。
色とりどりの折り紙で作った、今年の干支になる“巳”の折り紙なども含まれている。
今日は平日で、見学者はさほど多くなかったが、9日の日曜日には、ひな祭り弁当も110食準備されるらしく、大勢の人で賑わうことになろう。
|
|
|
|
| 2025年3月4日(火) |
| ひな祭りの夕食作り |
昨日と今日は2日続けて雨。しかもほぼ間断なく降って、ウォーキングにも出られないほど。
おかげで、雪はかなり消えたが、同時に小欄に載せる話題もない。
致し方なく、昨日作った夕食作りの話で、お茶を濁すことにする。
昨日はひな祭りの日である。若干なりともそれに相応しい料理を、と考えた。
ひな祭りらしい料理と考えたとき最初に思いついたのが、ばら寿司である。
材料を見ると鮭があった。
「鮭 バラ寿司」で検索をかけて出てきたレシピが次。
こちら→
幸い明太子もある。メインディッシュはこれでゆくことにした。
材料を焼いて混ぜるだけ。造作はない。
アレンジで海苔を乗せることにした。
使用した海苔は避難時食料として保管していたもの。 こちら→(2025/1/28)
最後の1枚が冷蔵庫で残っていたので、火で炙って味を復活し、乗せてみた。
次に考えたのが、ばら寿司に合いそうな品。材料を見ると、豆腐と白菜がある。
白菜は先日畑で採ったもの。 こちら→(2025/3/1)
これで検索をかけてみた。
出てきたレシピが次である。 こちら→
具合よく、鶏ひき肉もあるのでこのレシピを採用することにした。
調理法で難しいところはない。難なく作り終えた。
最後に残るのが汁。
普段夕食に味噌汁はほとんど作らないのだが、今回は味噌汁を作ることにした。
使うのはインスタント味噌汁の「あさげ」。これも先の海苔と同様に、避難時食糧の更新として出てきたもので、賞味期限切れのものである。
1人分の味噌汁の元を2人分の水で溶き、味を整えれば問題はない。
冷蔵庫にあるネギとウィンナー、そして先の「そぼろあん」で使う予定の豆腐を少しわけ、味噌汁の具材に入れることにした。
出来上がったみそ汁。器に盛った写真を撮り忘れた。
当日Mは仕事の日。仕事から帰ってのち一緒に食べる。
Mの評価は、三品とも概ね好評であった。
|
|
|
|
| 2025年3月3日(月) |
| 「事前指示書」の更新 |
今日の読売記事。
週一で掲載される、作家・久田恵氏の対談記事である。
今回の対談相手は、これも作家の吉永みち子氏。「事前指示書」のことについても触れている。
「事前指示書」については、Kもかなり以前に作成し、財布の中に入れて、常時持ち歩く体制はとっている。
ただ、記事にあるような、植物状態になったとき延命装置は「外して」という記載はしなかったという気がした。
いずれにしても、作成したのは随分以前のことで、ここで一度出してみて確認してみようかと思い始めた。
財布を出して取り出してみる。
ビニール袋に入れて保管してあるので、損傷は全く見られない。
文面を確認すると、作成日は平成30年12月とあり、8年前作成したもので、しかも、「辞退致します」と普段使い慣れない言葉を用いている。
誰かの文例を引用したものと思われるが、その時点では、作成の経緯を思い出すことができなかった。
取り敢えず今回の更新にあたっては、以前の文言はそのまま使用し、「除去」の言葉を追加して作り終え、元の形にして財布に収めたという次第である。
財布に収めて後、しばらく感慨にふけった。
財布に収めた事は記憶に残っていて、もうあれから8年も経ったのかという感慨であった。
その時思い至った事がある。
8年なら、作成経緯を小欄に載せているかもしれないという思いである。
調べてみると載せていた!
しかも、かなり詳細な記述である。 こちら→(2017/1/29)
引用したのは、樋口恵子氏の文例であった。
8年経ったが、樋口恵子氏もご健在、Kも有難いことに無事。
「事前指示書」が、今のところ「一種の保険」になっているものと思われる。
|
|
|
|
| 2025年3月2日(日) |
| Kがテレビに登場した |
Kがテレビに登場した。
といっても大した事ではない。邑南町が運営する地元のケーブルテレビでの話である。
「月間おおなんNEWS」という番組で、当該1ヶ月のうちに、邑南町内で開かれるイベントにつき一纏めにして放送するものである。
今回は2月分。放送は昨日の夕方から始まった。
録画をかけておいて、今日みたという次第である。
今回Kが登場したのは、2月9日に行われた、銭宝冬季オリンピックの模様。
こちら→(2025/2/9)
普段この番組はあまり熱心に見ないのだが、今回録画をかけてまで見たのは、当日ケーブルテレビのスタッフが来て競技を録画し、しかも終盤でインタビューを受け、カメラを向けられたからである。
ただし、結論的に言うと、受けたインタビューの模様は放送されなかった。
安堵したような、一方若干寂しいような、喜怒相半ばの印象である。
Kが登場したのは競技の部分。
Kが登場した部分を集中的に写して載せてみた。
”冬季オリンピック”が放送された時間は、5・6分という短いものであるが、その中では結構な頻度で登場していた。
当日は、吹雪くような悪天候で、参加者が少なかった性もあると思われる。
と、まあ、
話題の少ないこの時期の、苦し紛れの記事掲載を行ったという話である。
|
|
|
|
| 2025年3月1日(土) ラベル301 |
| 雪から掘り出した白菜で 鍋 |
2月下旬に襲われた第三次寒波の折りは、50cm程度雪が積もったが、この2,3日は温度があがり雪もかなり消えてきて、畑などの平地では10cm前後の雪になっている。
今日は夕食当番。台所周辺を探すが、葉物野菜が見当たらない。
畑に行けば、白菜などが雪の中から頭を出しているかもと思いつき、行ってみることにした。
覗いてみると、4、5個頭を出している。根を切断する包丁を取りに帰り、一株ほど白菜を収穫することにした。
抜いてみると結構立派な白菜であった。
白菜に思い至るまでは、別のメニューを頭に描いていたのだが、白菜があるとなるとまたもや鍋である。
白菜中心の鍋を作ることにした。
他にある材料を探すと豆腐と豚肉がある。
「白菜、豆腐、豚肉 鍋」で検索をかけることにした。
いくつか候補が出るが選んだのは次。すき焼き風の豚の鍋である。
こちら→
レシピでは、たまごは最後に鍋の中に割り入れる格好になっているが、ここでは取り皿に玉子を割り入れ、“牛好き”並みにつけて食べることにした。
食べてみると思いのほか美味。Mの評価も悪くない。
これまで“豚すき”の定番レシピを持ちえてなかったが、今回のレシピをその一つに加えてよいかもしれない、と思い始めている。
この田舎でも、昨今は野菜が極めて高い。
そんな折、畑に行って、雪をかきわければ白菜が取れる。田舎暮らしの醍醐味である。
|
|
